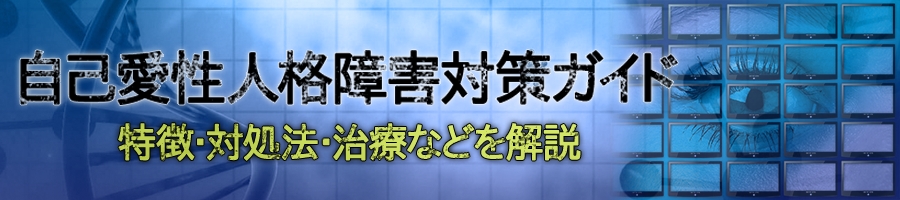スポンサーリンク
自己愛性人格障害の症状にみる幼少期の過ごし方
幼少期に見られる傾向−過保護の場合
自己愛性人格障害の症状がみられる場合、幼少期の過ごし方に共通点が見受けられます。自己愛性人格障害は「自分が特別である」「自分が中心だ」という考えが支配しています。大人になってもこの考えに至ってしまうのには2つの要因が考えられています。
過保護の場合には「自分はちやほやされて当たり前」という感覚から脱却するタイミングを奪われているといえます。小さいころは多かれ少なかれ自分が中心であるという発想はあるのですが、成長するにしたがって自然に「自分も尊重し、他人も尊重する」ことを覚えていくものなのです。
ところが、親からの行き過ぎたコントロールは「他人の尊重」ばかりを優先してしまいます。親の言う通りにさえしていれば親から褒められ、自尊心が満足する生活が続いていると、自分への尊厳とともに親以外の他人への尊厳も大切にできなくなってしまいます。
幼少期に見られる傾向−無関心、虐待
精神的な折り合いをつけられないのは、愛情に欠けた子ども時代をおくっていても同じ傾向がみられます。
幼いころに親や監督者から十分に愛情をかけてもらっていない場合、無意識にその理由を考えます。その際「自分が特別じゃないから愛情をかけてもらえないのだ」「自分が悪いから叩かれるのだ」という結論は到底受け入れられないものです。
ですから自らで「自分は特別な存在なのだ」と思いこまなければならないのです。相手の考えを尊重することは自分が特別であるということの否定であるととらえてしまうと、大人になっても相手の立場に立つことができません。
自己愛性人格障害の特徴的な症状である「自分は周りの人間にとって特別な存在でなければならない」という状態は、幼少期にバランスのとれた愛情、個々の子どもに見合った意思の尊重の仕方をされていなければなりません。
スポンサーリンク